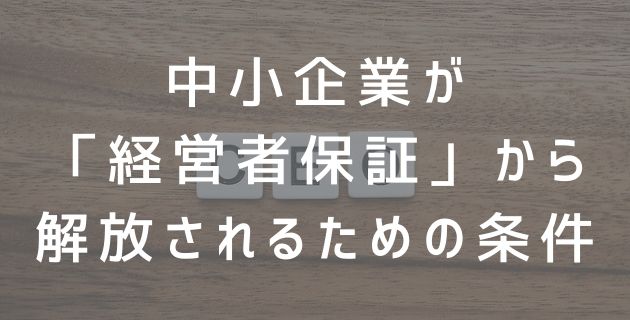民法改正で保証契約はどう変わったか?~改正民法の重要ポイント④
- 2020/6/19
- 法令コラム

中小企業が金融機関から融資を受ける際などには、連帯保証人が必要となることが少なくありません。しかし、融資を受ける企業の業績の詳細について正しい情報をもたないままに連帯保証人を引き受けたことで、予期せぬトラブルに巻き込まれるケースも珍しくありません。
このような問題に対応するために、4月から施行されている改正民法においては、事業向けの債務について個人が連帯保証する場合についてのルールが整備されることになりましたので、その重要なポイントについて解説していきます。
改正民法による新しいルールが適用される保証・根保証契約の範囲
民法改正によってルールが大きく変更されるのは、主債務を「事業のための負債」とする保証契約・根保証契約です。
「事業のための主債務」の典型例は、金融機関などからの金銭の借り入れ(貸金債権)ですが、それ以外の債務であっても、「事業のために負った負債」であれば新しいルールの対象となります。
たとえば、ビジネスにおいては、下記の契約に基づく債務を主債務とする保証契約が交わされることが少なくありませんが、これらにも新しいルールが適用されます。
- 事業用のリース契約
- 店舗・事務所などの事業用不動産の賃貸借契約
- 事業者間の継続的売買契約
主債務の事業該当性を判断する基準
主債務の事業該当性(事業のための負債であるかどうか)の判断は、主債務者がその債務を負担したときを基準時とし、その契約が締結された(金銭が貸し付けられた)ときの事情に基づいて判断されると解釈されています。
たとえば、事業目的で貸付の受ける場合には、その後の実際の用途に関わらず新しいルールが適用されることになりますし、これとは逆に、主債務者が事業以外の用途に用いる旨の説明をしていて、債権者も事業目的ではないとの認識があった(そう認識していたことに重大な過失がない)場合には、借り入れた金銭を事業目的に用いたとしても新しいルールは適用されないことになります。
とはいえ、今回の保証契約にかかるルール改正の主目的は「保証人の保護」にあるわけですから、主債務が脱法的な方法で負担された場合には、保証契約の効力が否定される余地は高いといえます。その意味では、事業該当性については、主債務者からの申告だけを基準とするのではなく、債権者側にも「事実上の調査義務がある」と考えておいた方がよいでしょう。
保証契約締結時のルール
連帯保証人が自ら締結した連帯保証契約について不測のトラブルに巻き込まれる原因の大半は、連帯保証契約の締結前に、主債務の内容や主債務者の返済能力について十分な情報を得られないことにあるといえます。
主債務者が親しい関係にある場合に「絶対に迷惑をかけない」という言葉以外に詳しい説明をしてもらえないまま、連帯保証人になることを断り切れなかったという場合が、その典型例といえます。
改正民法では、このようなトラブルを防止するために、保証契約の締結前の情報提供・意思確認のためのルールが設けられました。
主債務者の情報提供義務
| 民法465条の10(契約締結時の情報の提供義務) 第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 一 財産及び収支の状況 二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。 3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。 |
保証人になろうとする者にとって、主債務者の返済能力についての情報は、保証人を引き受けるかどうかを判断する上で最も重要な情報といえます。
しかしながら、保証人になろうとする者が主債務者の事業に直接関わっていない場合には、自力でその状況を正確に把握することは難しい場合も少なくありません。また、この点については主債務者とは利害が対立する場合も多く、主債務者の任意の対応だけでは十分な情報が提供されない可能性も低くないといえます。
そこで、改正民法は、「保証人になろうとする者への情報提供義務」を主債務者に課すという新たなルールを設けることにしました。
保証人になろうとする者に提供されなければならない情報
法律によって、提供が義務づけられているのは下記についての情報です。
- 財産及び収支の状況
- 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
- 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
これらの情報は、「保証人を引き受けるべきか否か」を正しく判断できるだけの程度で提供される必要があるといえます。したがって、「保有資産だけの開示」、「収入(毎月や毎年の売上げ額)だけの開示」では十分な情報提供がなされたとはいえません。一般的には、貸借対照表・損益計算書などの根拠資料に基づいて、幅広い情報の提供が必要となると理解しておくべきでしょう。
情報提供がなされなかった場合の効果と債権者側の確認義務
主たる債務者が情報提供義務を果たさずに保証契約が締結されてしまった場合には、保証人は、当該保証契約を取り消すことができます。
したがって、実際の保証契約の場面では、取消しのリスクを負担することになる債権者側に、「主たる債務者から提供された情報が適切であったかどうか」を事前にチェックする動機が発生するといえます。
さらには、これまでの判例などの動向なども加味すれば、債権者側には、自分のリスクを回避するための手段としてではなく、保証人保護(誠実な契約締結の担保)という観点から、「主債務者による情報提供が適切であったかどうかを確認・調査する義務」があると考える余地があることにも注意しておく必要があるでしょう。
事業のための負担についての保証契約における保証意思確認手続
| 民法465条の6(公正証書の作成と保証の効力) 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。 2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。 イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。 ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。 |
事業向け債務についての保証についての一番の問題は、主債務者が親族であることなどを理由に「情義」が優先し、保証人となるリスクを十分理解しないまま保証契約が締結されてしまうことにあります。
上で解説した保証契約締結前の主債務者による情報提供義務は、保証人となるリスクを正しく判断するために必要な条件と整えるための法整備といえますが、形式的な情報提供がなされただけでは、「情義的な保証契約」を抑制するには十分といえます。
売上げの減少などの保証人にとっては不安な情報があったとしても、主債務者からの懇願などにより、情報を正しく理解できない(リスクを十分に理解できない)ケースも起こりうるといえるからです。
そこで、改正民法においては、事業に係る債務について個人を保証人とする保証契約・根保証契約を締結する際には、当該保証契約などの締結に先立って、公証人による保証意思宣明公正証書作成しなければならないという新しいルールが設けられることになりました。
保証意思宣明公正証書を作成する手続
保証意思宣明公正証書は、簡単にいえば、保証人になろうとする者に「当該主債務について保証人(連帯保証人)になる意思が確かにある」ということを公正証書にしたものです。
したがって、保証意思宣明公正証書は、そのほかの公正証書を作成する場合と同様に、公証人によってのみ作成することができます。保証意思宣明公正証書を作成するための手数料は、保証契約1件につき11,000円となっています。
・保証意思宣明公正証書(日本公証人連合会ウェブページ)
また、この手続は、「保証人の真意」や「保証人となるリスクを理解している程度」を確認することが目的ですから、保証人になろうとする者本人によって手続がなされる必要があります(代理人によって行うことはできません)。
公証人によって確認される事項
保証意思宣明公正証書は、「保証人・連帯保証人になろうとする者が、そのリスクを十分に理解した上でもなお保証人・連帯保証人になる意思がある」ことを明らかにする目的で作成されます。
したがって、公証人の面前で確認される事項は「保証人・連帯保証人になる」という結論部分だけでなく、保証契約などの対象となる主債務の内容や、保証人(連帯保証人)が引き受けるべき責任の内容を「正しく理解しているかどうか」も対象となります。
また、公証人が保証人・連帯保証人になろうとする者がこれらの内容を「十分に理解していない」と判断したときには、保証意思宣明公正証書の作成を拒否する可能性があることにも注意しておく必要があります。
保証意思宣明公正証書が不要なケース(民法465条の9)
| 民法465条の9(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外) 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。 一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者 イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者 ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者 三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者 |
民法改正は、事業に係る債務についての個人による保証契約を抑制するものといえます。しかしながら、契約締結にかかるコストを重くし過ぎてしまえば、中小企業の資金調達に大きな支障を生じさせるデメリットが大きくなりすぎてしまいます。
そこで、主債務者の事業の状況を十分に把握することができ、保証のリスクを正しく認識しないまま保証契約を締結するおそれが低いと考えられる以下の者については、締結前の公正証書作成を不要としています。
- 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
- 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者
- 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
- 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式
- 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合における上記に準ずる者
- 法人以外の主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
本条の解釈の幅は狭い
本条で挙げられる保証意思宣明公正証書の適用対象外となる者の範囲は、厳格に解釈されるべきとされています。したがって、主債務者の経営を実質上支配していても取締役でもなく、株式の過半数を有さない者を保証人とする際には、保証意思宣明公正証書を作成しなければなりません。実際には従業員にすぎない「執行役員」という肩書きを持つ者についても同様です。
また、株式会社以外の場合についても同様に考えられますので「準ずる者」という文言を「株式会社の場合よりも広く解釈する余地はない」といえます。したがって、先代の経営者のように事業決定に大きな影響を持ちうる者であっても、法律上の業務執行権がない者を保証人とする際には保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。
個人事業主の場合の共同経営者や事業に現に従事している主債務者の配偶者についても、出資しているのみに過ぎない者であれば共同経営者とはいえませんし、従業員として働いているに過ぎない主債務者の配偶者や、内縁関係に過ぎない者を保証人とする際には保証意思宣明公正証書の作成が必要です。
保証契約締結後のルール
| 民法458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務) 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。 民法458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務) 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。 2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。 3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。 |
改正民法においては、保証人の保護をさらに徹底するために、保証契約が締結された後も債権者に対して次のような新たな義務を定めることにしています。
- 主債務の履行状況に関する情報提供義務(民法458条の2)
- 主債務者が期限の利益を喪失したときの通知義務(民法458条の3)
このうち、期限の利益を喪失した際の通知義務は、それを怠った場合には、期限の利益喪失後から保証人への通知が行われるまでの遅延損害金の請求権を失権することになることに注意しておく必要があります。とはいえ、主債務者が期限の利益を喪失した場合の通知は、これまでも債権者側できちんと対応している場合が多いといえますので、実務上の影響は小さいといえるでしょう。
根保証契約における極度額の事前設定義務
| (個人根保証契約の保証人の責任等) 第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。 2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。 |
事業上の取引関係は中長期にわたる継続的なものになることが多く、根保証契約はとても便利な仕組みといえます。
その反面、根保証人のリスクは、単独保証の場合に比してかなり高いといえますが、法律に詳しくない一般個人が根保証人となるケースでは、根保証制度そのものについての理解が不十分というケースも少なくありません
そこで、根保証人が根保証契約時に予想していなかった責任を負わされたことで、生活が破壊されるような事態を回避し、根保証人になろうとする者が自ら負担しなければならないリスクを可視化できるようにするために、改正民法においては、根保証契約の締結に際しては事前に具体的な極度額を設定しなければならない旨の規定を新設しています(民法465条の2第2項)。
この極度額は「具体的な金額」を明示する必要があると解釈されていますので、たとえば、「滞納家賃の4ヶ月分」といったような極度額の定め方では不十分とされる可能性が高いといえます。
民法改正で保証契約はどう変わったか:まとめ
事業に関する負債の個人保証は、中小企業の資金調達におけるリスクを保証人の負担に転嫁させた仕組みといえる点で、必ずしもフェアな契約とはいえない側面があります。実際にも、個人保証が原因で、保証人の生活が破壊されたり、保証人に迷惑をかけてしまうことを懸念して企業の負債処理(債務整理・経営再建)が後手になってしまう弊害は、さまざまな場面で指摘されています。
平成26年2月に経営者保証に関するガイドラインの適用がはじまったことで、近年では政府系金融機関を中心に、事業向けの融資に個人保証を求めないケースが増えています。
今回の民法改正も、事業向け融資に際して個人保証を求める場合の主債務者・債権者の負担を大きくすることで、事務業務家融資への個人保証を抑制することを狙ったものといえるでしょう。
また、このような流れは、中小企業にとっては「保証人さえ用意できれば資金調達できる」という考え方からの脱却を迫るものといえます。したがって、今回の保証契約についての民法改正は、「ルールが変わった」という程度にとどまらず、今後の資金調達のあり方(企業経営のあり方)それ自体を変えうるだけの影響力があるといえるでしょう。
中小企業が「経営者保証」から解放されるための条件~経営者保証ガイドラインの概要と内部統制との関係